ひつこく伝授したい「飽きない丼物」
佐藤です。
先日、「天津飯を上手く作るには?」というご質問を頂きました。
今回は、それを伝授したいと思います。
おすすめの、「和風天津飯」は、今まで何度か伝授してきましたが、”切る”作業が一切ないので手軽に作れて、15分程度の時短料理。
とにかく腹を膨らませたい時にピッタリの”丼めし”でもあります。
ごはんと玉子、それとみりん、醤油などの調味料あれば、今すぐにでも取りかかれます。
私自信、「天津飯」が大好きなので、毎日ひつこいくらいに伝授したいです。
お店の”まかない”でも何回作ったか分からないほどたくさん作ってきました。
家でも作ることが多いので、今までに100回以上は作ったと思います。
まかないで作れば、アルバイトの子に「佐藤さん、旨いっす!おかわりしていいですか?」と言われましたし、
家で作って家族に、ばれないようこそっと食べた時は、あ~やっぱり旨いわ!」としか思えません。
で、この「和風天津飯」は、作るたびに新しい発見があり、「こうすればさらに美味しくなる」というのがわかり、
リメイクするたびに”コツ”を書き加えたり、分かりやすい表現を変えたりしてきました。
なので、今回のレシピも今まで紹介したレシピと一部矛盾点があるかもしれません。
(今回書き加えたコツは、餡をさらに美味しくする方法です)
が、今回の「和風天津飯」のレシピが現時点でのほぼ完成版。
なので、自信持って伝授できます。
料理の向上にゴールはないので美味しくできる”コツ”を発見した時はまた、伝授したいと思います。
では、「餡を上手く作る方法」もわかるレシピをすぐに見て下さい
↓↓
【材料】
玉子(L玉)・・・3個
サラダ油・・・20cc
ごはん・・・好きなだけ
刻みネギ・・・少量
【和風あん】「10:1:1」の割合
・水・・・300cc
・みりん・・・30cc
・うす口しょうゆ・・・30cc
(濃口しょうゆを少し(小さじ1/2杯)加えると
風味がよくなります)
・砂糖・・・小さじ2
(甘いほうが好みの場合だけ入れて下さい)
・粉かつお節・・・小さじ1 (2g)>
・水溶き片栗粉・・・45cc
(片栗粉20gと水25ccを混ぜる)
※餡に麻油を少~し加えると”コク”が
出てさらに美味しいです

だしを混ぜながら水溶き片栗粉を加えていきます。
※注意!必ず沸騰している状態(中火のまま)で入れて下さい。
水溶き片栗粉を出し汁に早く溶け込ますように玉じゃくしで混ぜます。
(素早く混ぜないと片栗粉の塊りができ、”失敗あん”になります)

(食べている間にとろみ感がなくなってくる”偽者とろみ”です)
ここからさらに”1~2分”混ぜながら加熱します。
(混ぜ続けてください!)
(少し難しいですが”最も手に抵抗を感じた段階を過ぎて
『少し軽くなったかな』と思う状態まで加熱をつづけるのが目安です)
火を止めて”和風あん”の完成です!
(ここで胡麻油(サラダ油などでもOK)を少量加えるとコクが増してさらに旨いです)

殻が入ったら取り除いてください。
(白いへその尾みたいなものは、栄養があるのでそのまま混ぜます)
黄身を潰します。菜箸をボウルの底に付けたまま縦、横 交互に上下左右に動かし、最後は回して混ぜます。
白身と黄身が混ざったらOK

(ご飯が冷めないようにするため)

(お茶碗1杯~1.5杯が目安)

煙が出だしたら、フライパンを一度火から離し中火にします。
10秒後、火に戻し混ぜた玉子をイッキに流し入れます。

外側から固まってくるので、それを内側に入れるように混ぜて固めていきます。(できるだけ円形になるように固めます)素早く行ってください。(玉子に焦げ目(茶色)が付くとマズそうに見えるので)

「半生スクランブルエッグ」を作るつもりで焼きます。

もし、できそうならフライパンを勢いよくふって玉子を裏返してください。
すぐ火を止めます。
裏側は、表面が少し固まればOKです。



「あん」はタップリ多めのほうが美味しいです。
一滴残らず、かけてください。

さらに「餡を美味しく、上手く作る”コツ”」は、こちら↓↓を見てください
「餡のとろみの付け方3つの”コツ”」






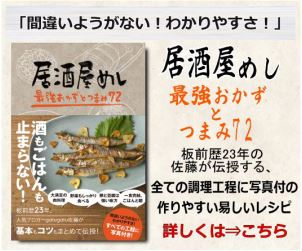




























この記事へのコメントはありません。