【茹でる基本を省いて栄養素たっぷりの一品】
健幸料理家 佐藤周生です。
「炒め煮」という調理法は、ご存知でしょうか?
ほとんどの方が知っておられると思いますが、字のごとく
「食材を炒めて煮る」調理法です。
油で炒めてから煮ると油がコクとなって香ばしさが加わり、美味しくなります。
また、アクの強い菜っ葉などは、その香ばしさでアクのエグミが少し和らぐのですね。
みんなが知っている炒め煮を活用した代表料理の1つは、
「筑前煮」。
大根・人参・れんこん・ごぼう・こんにゃく・たけのこ・鶏肉などを甘辛く味付けした和食の定番煮物ですよね。
筑前煮は、通常の煮物のように煮る調理だけでなく、油で炒める作業があることでコクと香ばしさ加わって美味しいのですね。
胡麻油で炒めるとさらに風味が増して美味しいということ。
また、筑前煮は食材のほとんどが根菜類なのでアクが多く、油で炒めることでエグミを抑えることもできます。
(※お店で筑前煮を作る時は(というか本来の作り方)、食材それぞれ下茹ででアク抜きして、それからまとめて炒め煮にするのでエグミを感じません…だから、お店の筑前煮は美味しいわけです。お店によりますが…)
で、この炒め煮は菜っ葉類で作っても美味しいのですが、
例えば、小松菜ならエグミが結構強い。(葉っぱがエグイ)
なので、炒めただけではそのエグミを強く抑えることができない…
よって、下茹でしてから「炒め煮」にするほうが、味的には美味しくできるわけです。
ですが、エグミや苦みは栄養素そのもの…
老化を防止してくれる抗酸化作用あるポリフェノールなどです。
「下茹で」作業は料理の基本ではありますが、以前お伝えした通り、栄養素の多くは水分にすごく溶ける。
要は、茹でることで茹で汁に栄養が溶け出てしまうわけです。(茹で汁を飲めば栄養素は摂れますが…)
さらに僅かですが、加熱による栄養素の消失もあるので、茹でる加熱で栄養素を少し失い、さらに炒め煮で加熱するとなれば、失う栄養は多くなります。
味や見栄えより、体のことを考え「健康のために食べる料理」を優先するなら、「下茹で」は省いたほうが良いわけですね。
「茹でる」という料理の基本は、栄養価を下げてしまうということを忘れないで頂きたいです。
そもそも、現代の野菜は短期栽培によって太陽にあたる期間が短く、栄養価が低いですから下茹ですればその貴重な栄養素を無駄にすることになります。
「それじゃ、小松菜みたいなエグミの強い野菜は炒め煮にしても美味しくないのか?」
というと、もちろんそんなことは無いです。
下茹で無しの炒め煮はエグミが残りますが、食べられないほどのエグミでは無いです。
「生のたけのこ」の煮物を食べたことがあれば分かると思いますが、ちょっとエグミを感じますよね。
調理法によってはエグミを強く感じることもあります。
とはいえ、後味でちょっとエグミを感じるくらいではないでしょうか。
小松菜の炒め煮はそれよりも弱いエグミです。
また、若干濃い味付けにすれば、エグミは抑えられますから、エグ過ぎて食べにくいなんてことはありません。
何より「下茹で」の作業が無いということは調理を時間短縮できるので、料理が楽になるでしょ?
ということで、今回のおすすめは「下茹で」を省いた、
ズボラ「小松菜の炒め煮」です。
彩りに人参を加え、人参と小松菜を油で炒めてあっさり煮汁で7分煮るだけ。
1日以上冷蔵庫で寝かせれば、味がしっかり滲みてエグミも感じにくくなります。
簡単に作れる副菜&お総菜の一品としてマスターして頂きたい。
「炒め煮」という調理法を習得しておくことで、
小松菜を法蓮草・水菜・チンゲン菜などに代えるだけで簡単に応用でき、レパートリーも拡大しますよ!
レシピみて下さい。
↓↓
【材料】(2~3人前)
小松菜…1/2束(200g)
人参(中)…1/8本(20g)
油…小さじ1杯
【煮汁】
割合『出汁10:みりん1:淡口しょう油1』+酒少量
水…大さじ10杯(150cc)
粉カツオ節…小さじ2杯
みりん…大さじ1杯(15cc)
酒…小さじ2杯(10cc)
淡口しょう油…大さじ1杯 (15cc)

水気を切ります。


※葉の横幅を短くするため。



フライパンを強火にかけ、油(小さじ2杯)を敷き、30秒ほど熱したら中火に。
人参を入れて炒めます。


水(150cc)、粉カツオ節(小2)、みりん(大1)、淡口しょう油(大1)の順で加えます。



※団扇であおぐなどしてすぐに冷まして下さい。
熱いまま置くと小松菜の綺麗な青色が茶色っぽくなり、見た目が悪くなります。


寝かせることで味が滲みて美味しくなります。

さらに途中(1日後)、混ぜることで絡んだ菜っ葉がほぐれて味が滲み込みやすくなります。
絡んだ部分は中まで、なかなか味が入っていかないので。
是非、作って下さい。









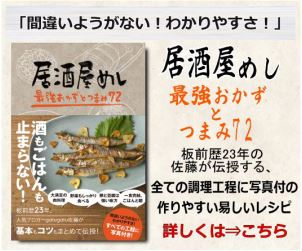
























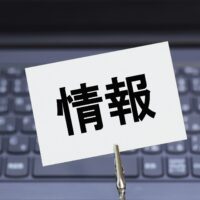




この記事へのコメントはありません。